もの作りの原点をたどります。
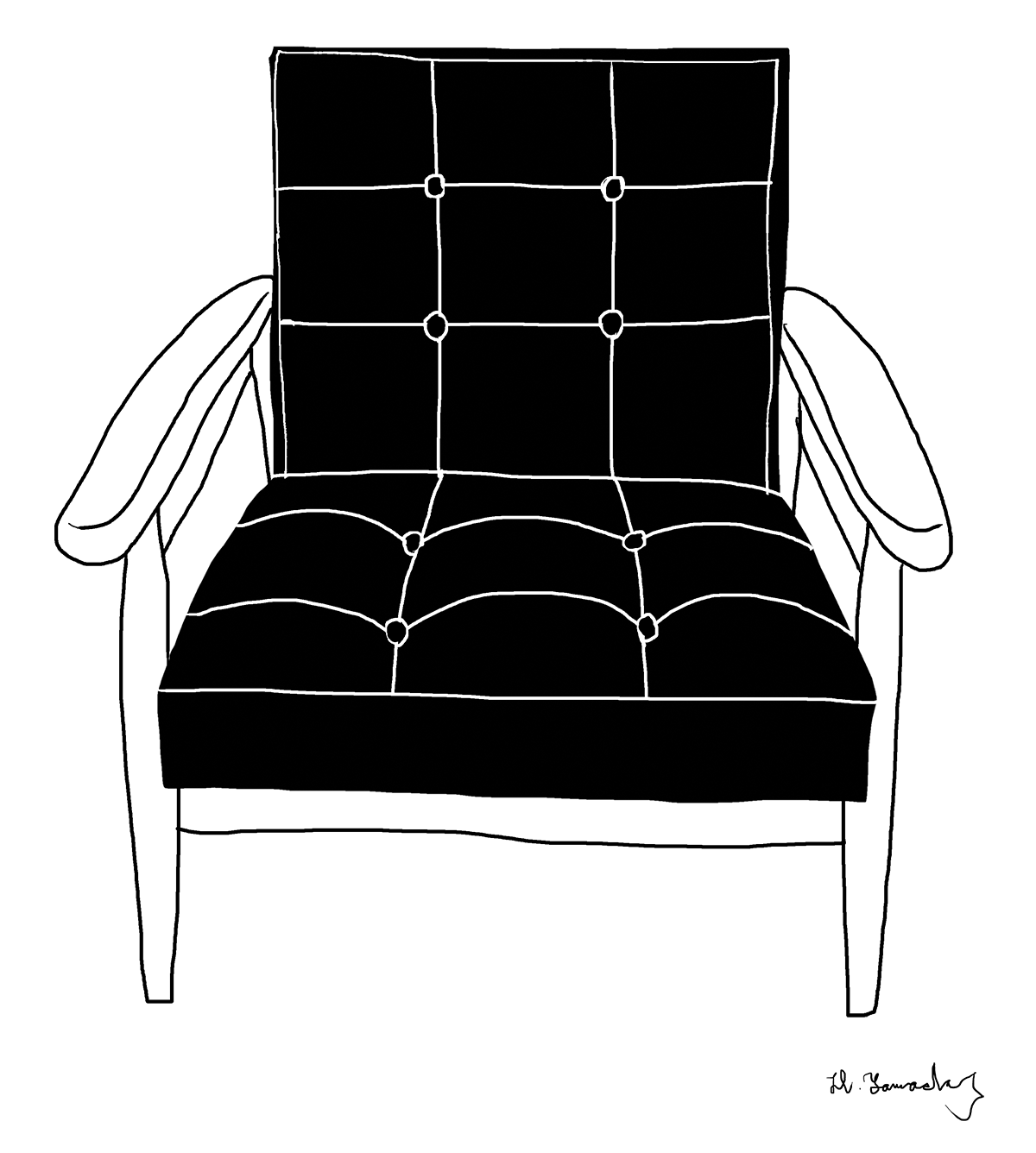
僕らがKチェアを作った頃
東京オリンピックの開催を数年後に控えた日本。社会全体が高度経済成長に沸き、ちゃぶ台からダイニングテーブルへとライフスタイルは変化しつつあった。そうした時代に「Kチェア」は誕生した。製作に携わった人々はどんな思いでこの椅子を生み出したのか。家具の会社カリモクの黎明期を支えた人々に話を聞いた。

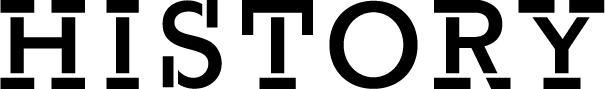
もの作りの原点をたどります。
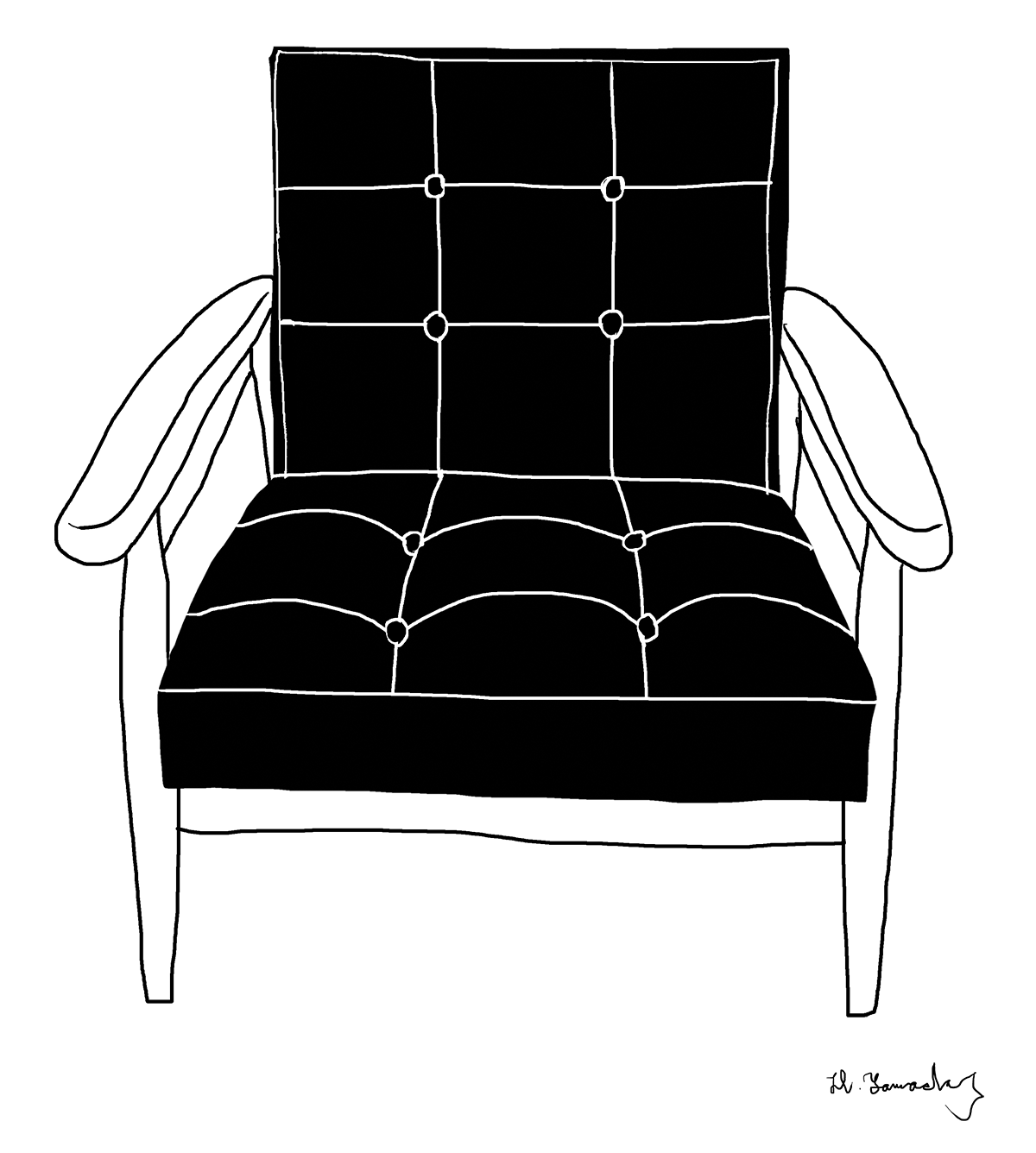
東京オリンピックの開催を数年後に控えた日本。社会全体が高度経済成長に沸き、ちゃぶ台からダイニングテーブルへとライフスタイルは変化しつつあった。そうした時代に「Kチェア」は誕生した。製作に携わった人々はどんな思いでこの椅子を生み出したのか。家具の会社カリモクの黎明期を支えた人々に話を聞いた。

1962(昭和37)年は、カリモクにとって記念すべき年だ。この年、カリモクは国内向け自社製品の第一号となった製品番号1000番の椅子を発売し、家具会社としての歩みを始めた。そして、この1000番の椅子がのちに誕生する「Kチェア」の原型となる。
1940(昭和15)年、刈谷市の小さな木工所からスタートした。以来、カリモクでは梱包用の木箱やミシンテーブル、ピアノの部品などさまざまな木工製品を下請けとして生産してきた。だが下請けでは景気の浮き沈みに翻弄されてしまう。そこで安定的な経営を目指すため、これからは自分たちの製品を作って売っていこうと決意する。家具という新たな分野へ飛び込んだのは、その3年ほど前からアメリカに輸出する木製のアームチェアを手がけていたからだった。折しも日本では、住宅事情が大きく変化していた頃。間取りにダイニングキッチンやリビングが登場するようになり、畳の和室からカーペット敷きの洋室が増えていた。そこでこれからは洋家具の需要が伸びるだろうと考えたのだ。
そうして完成した1000番は、ゆったりと腰を掛けられるスクエア型の布張り木肘椅子だった。それはアメリカに輸出した木製アームチェアを日本人の体に合わせ、より洗練した形にデザインし直したものだった。1000番はその後さらに直線的なラインへと改良され、WS 1150番と呼ばれていた「Kチェア」になった。
デザインを担当したのは、故・奥山五男。アメリカ輸出用の椅子も手がけ、カリモクが家具会社としてスタートを切ったときからメインデザイナーとして活躍した人物だ。奥山はデザインのみならず、品質にも人一倍こだわった。「初めて自分たちの名前で出す家具だから、基準も自分たちで厳しく作りました」と語るのは、カリモクOBの林隆嗣(たかつぐ)。1967年に入社し、奥山の下で「Kチェア」2シーター、「ロビーチェア」、「リビングテーブル」などの図面作成を手がけた。「家具生産が盛んなデンマークでは、高い品質を維持するために家具品質管理委員会という組織がありまして。そこの基準を奥山さんが持ってきて、僕らはこれより上にいかないといかんと。だから『Kチェア』は、いわばカリモクの品質基準を作った椅子ですわ」
そうして始まった家具作り。当時は、何でも作ったら売れる時代だった。次から次へと新しい応接セットが作られ、市場に出ていった。当時の忙しさを林はこう振り返る。「入って2日目で、奥山さんが描いた絵からおこした椅子の図面を渡されて、これに合うセンターテーブルの図面を描けって言われて。いきなりですよ。その日から奥山さんが絵を描き、私が図面にして、すぐ試作に入る。現場でここをもうちょっと太くしようとやりとりしながら、1週間もしたら完成するといった具合で、新しいものがどんどんできあがっていきました」
そうして見る見るうちにカリモクは家具メーカーとしての地位を確立していく。だが、そこに至るまでには右も左もわからないなかで家具を作り始めた苦労もあった。

刈谷木材工業正門付近。製材木取工場や乾燥室が作られ、設備が充実してきたころ。木工には欠かせない木材乾燥技術が大きく進歩していきました。

高度経済成長期に入り、カリモクでは、ステレオキャビネットや白黒テレビの木部を作り始めました。右端は片山辰美(たつみ)。

欧州の家具メーカーとの契約のために訪れたパリ。後列左は林隆嗣、後列中央は林の上司の奥山五男。モンマルトルの丘で。
「カリモクはもともと木製品はお手のものだったんです」と、家具作りに最初から携わってきたカリモクOBの片山辰美は言う。「問題はクッションをどうするか。木工会社ですから、“張り”という言葉自体初めて聞くわけです。そこで私とほか2人の社員が1年間で“張り”の技術を習得してこいとなったんです」
最初は、椅子張り屋に丁稚奉公に入った。そこで朝から晩まで、座面の底に麻テープをはる作業をやらされた。しかし、3か月間経ってもこの作業から一向に先に進まない。片山は会社に戻り、工場長に「このままでは1年でとてもマスターできません」と訴えた。そこで今度は別の工作所を紹介してもらう。
最初にその工作所を訪れたとき、親方には「ゴールイメージは何だ」と聞かれ、片山は「図々しいですが、1年後にカリモクの中に張り加工のラインを作って椅子を生産したいです」と腹を割って答えた。すると、親方は頭を抱えてしまった。だが彼らの切羽詰まった思いが通じたのだろう、親方は「じゃあ、年間の計画を立てよう」と言ってくれた。
当時はまだハサミで反物を裁っていた時代。いまなら機械で一瞬のうちに裁断されるが、その頃はハサミの使い方からまず覚えなければいけなかった。革や布を木枠に張り込むのも、現在はタッカーという大きなホチキスのような道具を使うが、当時はそれもない。まとめて口に含んだ小さな釘を、1本ずつハンマーでトントンと打ちつける。口に含むのは、打ったあとに唾液で釘が錆びて抜けにくくするためだ。まさに職人技の世界だった。
3人は裁断から始まり、ウレタンフォームの接着方法、底張り、工業用ミシンの縫い方まで順に学んでいった。ちゃんと縫えるようになるまで、3人とも懸命にミシンを踏み続けた。そして最後には、縫製品をフレームに着せて椅子に仕上げるという一番の難関が待ち構えていた。
ちょうどそのとき、工作所にはパチンコ屋の丸いスツールの注文が大量に入っていたのを、彼らが担当した。「パチンコ屋のスツールには、座面のまわりにぐるっと玉縁(たまぶち)というパイピングがついています。それを張るのがむずかしくて。少しでも油断すると、玉縁がぐにゃぐにゃですわ。注意して張らないと、ぴしっとまっすぐにできないんです」と、当時を振り返る。失敗すると親方は、「売りものにならん」とハサミで切ってしまう。そうなると、またミシンからやり直しである。来る日も来る日も同じ作業に明け暮れた。そして2か月がすぎた頃、親方から「これならまあいいな」と言われるぐらいにやっと上達した。
カリモクの工場に戻った片山たちは休む間もなく、今度はラインの立ち上げに取りかかった。見かねた工作所の親方夫妻も1か月、指導に来てくれた。親方は作業を監督し、ミシンの達人の奥さんは、女性社員を1か月マンツーマンでみっちり教えてくれた。ただ、それでもまだ不安は残った。「ラインを作ったのはいいけれど、本当に値段をつけて売ることができる商品ができるかどうか。親方に言わせれば、いまは70、80%の出来。100%にするため、あと残りをどうすればいいか。そこで親方に相談したんです。どこかに職人さんいませんかって」
そうして教えてもらった京都の職人のところへ、工場長と片山はすぐさま向かった。その職人は国家資格の一級家具製作(椅子張り作業)技能士で、宮内庁御用達の家具製作の仕事を専門にやっていたプロ中のプロだった。渋る職人を前に、2人は「金は出しますが、口は出しません」と言って必至に説得した。片山はそのときの思いをこう振り返る。「5年先、10年先の会社のことを考えたとき、今のレベルから自分たちが上達していくとは思えませんでした。だからぜひとも、自分たちの先生が必要だったんです。その職人の方に来ていただいたおかげで今日のカリモクがあります」。
そうしてなんとか椅子張りのラインが稼働し始めた。しかし、最初の頃は新製品を作るたびに試行錯誤が続いた。「最初はボタンを作ることすら知らなかったんです。スーパーで既製品を買ってくるわけにはいかないし」と片山は言う。それでボタンを成形する機械があると教えてもらい、導入する。椅子の生地でボタンが作れるようになると、今度は取れにくいボタンつけの糸を探さなければいけない。そんな具合で、文字どおり一つひとつ問題をクリアしながら生産体制を整えていったのだ。


1973年3〜5月の総合カタログ「カリモクの家具」で紹介されている「Kチェア」のセット。「Kチェア」スタンダードブラック、タープグリーンとほぼ変わらない姿。
「よくあれだけの新製品を次から次へと作ったもんですよね」と、林と片山は言い合う。 最初の頃はトラブルも少なくなかった。「箱を開けたら右肘が2本入ってたとか、組み立てに必要な穴が開いてなかったりとか。ノックダウン方式だったのでずいぶん助かりましたよ。パーツだけ取り替えれば済んだから」と、片山は笑いながら語る。林も「カリモクの家具は持ちにくいと家具屋さんに怒られたこともあります」と続ける。サイドボードなどの箱もので、収納力を上げるために天板の後ろぎりぎりのところに裏板をつけていたら、それだと手がかからないとクレームが来たのだ。そこですぐに裏板を天板より少し落とし込む設計に変えた。いまのカリモクでは考えられないようなトラブルも多かったのだ。こうして大勢の助けや指摘を受けながら、カリモクの家具は磨かれていった。
最後に林はこう言った。「若い人に言うんです。経験しなさいと。経験が人を育てるんだから。最初からできる人なんて誰もいないです。やったからできるようになるんです」。また、片山は「当時の私たちは、暇さえあれば本物を見に行きました。女性が持っているバッグも代表的な革製品ですから、もちろん見ました。本物を見ないと、本物は作れませんよね」と語った。家具は決して安い買いものではない。できれば気に入ったものを長く使いたいと思うものだ。だからこそ、無責任には作れない。「ぽっと作って1、2年で辞めるというより、ずっと作り続けられるものをデザインしようとやってきました。家具が好きで少しずつ揃えていくお客さんに対して、気に入った家具の相棒を買い足せるようにするのも家具メーカーの仕事の一つでしょ」。家具を作り始めた頃から変わらずにいる「Kチェア」は、まさにその言葉を裏づける存在だ。どんな思いで家具を作ろうとし、どういままで歩んできたのか。「Kチェア」は、カリモクのもの作りの歴史をいまに物語っている。

カリモク60が立ち上がった時点の「Kチェア」 1シーターのラインナップ。タープグリーン(右端)は当初、「Kチェアの原型1000番を表現したい」という理由で、キルティング加工はありませんでした。