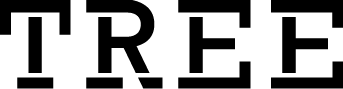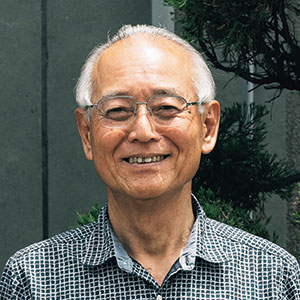COLUMN
一覧に戻る木のはなし
未来を見据えた先に
たどり着いたラバートリー
取材中、執行は「昔より今のほうが職人的な仕事が求められています」と語った。かつては「ナラを使うならこのデザイン」と、樹種によって作るものが決まっていた。しかし、今では同じデザインでもいろんな樹種を選べるようになった。樹種が変われば当然、木取りも加工の仕方も変わってくる。
「手間がかつてにくらべて、4倍、5倍に増えています。自動化で流すことがどんどん難しくなっていますね」。それでもいろんな材を使うのには、理由がある。一つには、お客様の選択肢が広がるため。そしてもう一つには、在庫切れのリスクを回避するためだ。「一つの樹種に人気が集中してしまうと、すぐに材料が切れてしまいます。一度切り尽くしてしまったら、また使えるようになるまで木が育つには、何十年と時間がかかります」
現在、「Kチェア」ではラバートリーがメインで使われている。だが、発売当初は国産材を使っていた。樹種を変えたのは、国内で木材の調達がむずかしくなったからだ。「1960年代から70年代は、ブナが切りどきでした。当時は高度経済成長期で家具が作っては売れていましたから、使えるブナ材をすべて切ってしまったんです。家具に使える大きさにまで、ブナが成長するには120年かかります。そこで今度は、北海道や東北のナラに人気が集中しました」
しかし、ナラがいずれ枯渇するのも目に見えていた。そこで新たな材を求めて国外へ出ていき、目をつけたのがマレーシアのラバートリーだった。ゴムの木は植えてから5、6年でゴムの樹液が取れるまでに大きく成長する。その後、樹液が出なくなると伐採され、新たに植林される。伐採された材はただ焼かれていた。そこに注目をしたのだ。
「これから57億人の世界中の人々が木を使い出したら、温帯、熱帯の木はすぐになくなってしまうだろう。でも30年で育つこの木には未来がある。だから、自分はマレーシアに出てきたんだ」
マレーシアの工場を立ち上げ、現在カリモク家具の相談役を務める加藤英二はかつてそう語ったという。「今や世界の人口は70億人を突破しています。これからますます、木材の確保はむずかしくなるなか、ラバートリーは環境にも負担が少なく、非常に有効な材だと思います」
ただ、ラバートリーは、幅の広い材が取りにくい、表面が毛羽立っているなどの欠点も多い。そのため採用するにあたっては接合方法や表面の特殊処理など、独自の技術を改良する必要もあった。
そうした問題を解決して、製品化にこぎつけたのが1982年。1988年にはカリモクマレーシアを設立し、以来、ラバートリーを安定的に供給できるようになった。
- 木目 / 年輪
- 木目は、年輪や木の繊維が織りなす模様。木々は春夏に膜の薄い大きな細胞を作りながら、幹を太らせ、葉を茂らせる。秋になると、成長のスピードは遅くなり、膜の厚い小さな細胞を形成するようになる。年輪は、その粗い細胞と密な細胞のコントラストが輪のように現れたもので、木が育った環境や樹齢によって一本、一本異なる。1年に一度刻まれた年輪が、幾多の歳月を経て、おおらかな木目の模様を描き出している。
- 柾目(まさめ) / 板目
- 柾目は、丸太の中心に向かって挽いたときに年輪が平行に現れる木目のこと。板目は、丸太の中心からずれて挽いたときに年輪が平行ではなく、山形や筍形に現れる木目を指す。柾目板は伸縮の度合いが小さいが、幅が広い板は取りにくい。一方、板目板は幅を広く取ることができるが、伸縮の度合いは大きい。用途やコストに応じて、柾目と板目のどちらにするかが使い分けられている。
森から考える
100年サイクルの家具作り
先のラバートリーをはじめ、カリモクはこれまで新しい材料を積極的に取り入れてきた。昨今、人気があるのはウォールナットやチェリー、メープルなどの北米産の木材だ。ほんの5年前までは、パイン材などの白木が人気だった。だが、この3年ほどで落ち着いた色合いのものへと流行が移り変わっていった。
「ずいぶん前からウォールナットで試作して提案してきたんですが、なかなか通りませんでした。それがここ数年で急激に使用量が増えて。まさに時代が呼ぶんだなと思いました。だから、焦らずにじっくりといろんな材を提案していこうと思います」
もちろん、木なら何でもいいというわけではない。日々の生活のなかで、家具にはいろんな力が加わる。長く使い続けるためには、当然丈夫でなければいけない。そのためカリモクでは、自社で設定した硬度と強度の厳しい基準をクリアしなければ、家具材として使用できないことになっている。
執行には、ずっと抱き続けている思いがある。それは「日本のメーカーなのだから、できれば輸入材に頼らずに、日本の木を使って作りたい」というものだ。
「弊社のように量産メーカーの場合、ある程度まとまった数の材料を確保する必要があります。しかし現状、日本で伐採されている木を採用しようとすると、少し売れただけでもすぐに量が足りなくなってしまう。でも日本には、使われていない木もまだたくさんあります。そうした木をどうにか生かす方向を模索していきたいと思っています」

そのための研究は怠らない。知多カリモクの加藤洋社長は珍しい材料を集めるのが好きで、そのコレクションは工場の一角の棚に保管されている。実際、その棚にあった材料を使って試作し、製品化されたものもある。
また、同社の敷地には木々を試験的に植えている通称「カリモクの森」もある。つい最近も、九州に自生している早生の落葉広葉樹を植えたばかりだと、執行はうれしそうに話してくれた。
木という素材の特異さで、一つ言い残したことがある。それは、伐採してもまた植えれば育つということ。問題なのは木を切ることそれ自体にあるのではなく、森のサイクルを破壊して、維持できない状態にしてしまうことだ。
百年かけて育った木を使うのだから、百年使える家具を作る。そして、その百年の間に新たな木を育てる。カリモクの家具作りは、森を考えるところから始まっている。
- 木の硬度 / 木の強度
- 木材の丈夫さを示す指標は、硬度と強度の二つがある。硬度は、表面の傷つきやすさを示すもの。たとえば硬度が低いと、引っ掻いただけで簡単に傷ができる。日本では今、スギが切りどきを迎えているが、カリモクでスギを使わない理由は、硬度が低く、鉛筆で文字を書いただけでも傷ができるからだ。一方、強度とは力を加えたときにどれだけ耐えられるかを測るもの。強度が低いと、ある一定の力を加えるとポキッと折れる。代表的な強度の低い木としては、彫刻などで使われるホウノキやカツラなどが挙げられる。カリモクでは硬度と強度を測るために実際に試作を行い、さまざまなテストをクリアした材だけを使っている。


- Text:
- Yuko Shibukawa
- Photo:
- Shintaro Yamanaka(Qsyum!)